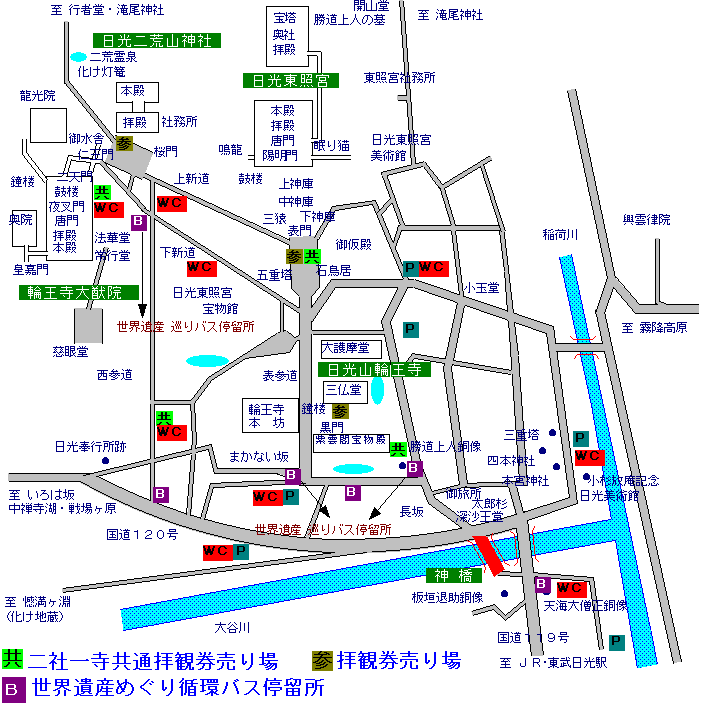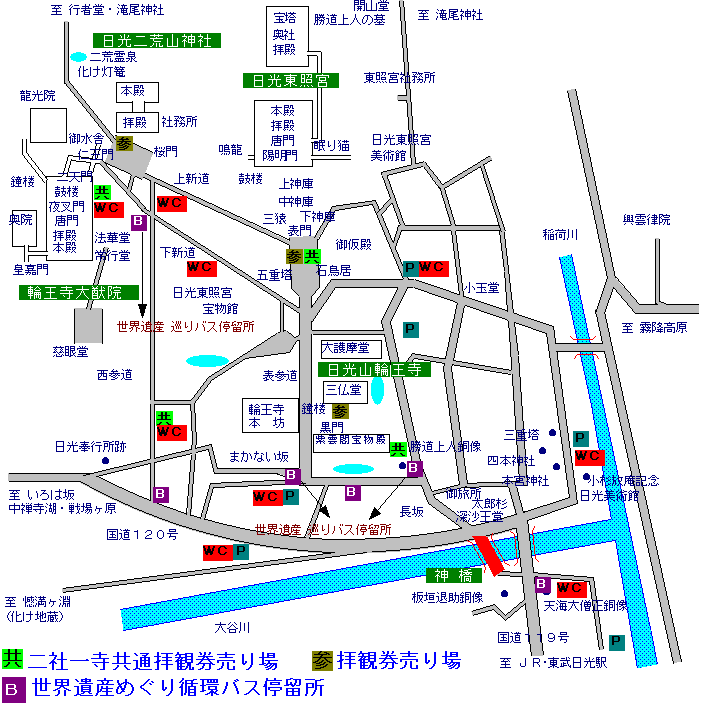|
264年に及ぶ「徳川幕府」を作り上げた初代将軍:徳川家康を祀った神社。
家康自身の「遺体を静岡県の久能山におさめ一周忌の後、日光に小さい堂を建てて神として祀ること。」という遺言により、1617年、息子である二代将軍:秀忠によって建立された。
当初は比較的質素な作りだったが、祖父:家康を敬愛してやまない三代将軍:家光により、1636年「寛永の大造替」によって現在の絢爛豪華な形となった。この大改装の費用は現在の金額に換算すると500億円以上とも言われている。また特筆すべきは巨費だけではなく、当時の優れた建築士、大工、塗り物師などを全国から集め建築技術・工芸技術・美術の粋を結集した建築物となっていることである。
また、建立にあっては陰陽道の影響を強く受けており、境内の主要な建物を結ぶと北斗七星の形になるよう設計されている他、鳥居・陽明門・唐門・本殿を結ぶ延長線上に北極星が来るように建物が配置され、更にはその線を南に伸ばすと江戸に当たるよう、つまり江戸のほぼ真北に、位置するように建立されている。
1999年、日光山輪王寺・日光二荒山神社と共に「世界遺産」に認定された。 |
| 主な伝統行事 |
| 1月 |
1日 |
歳旦祭 |
|
2・3日 |
新年献饌祭 |
| 2月 |
3日 |
節分祭 |
| |
11日 |
紀元祭 |
|
17日 |
祈年祭 |
| 4月 |
14日 |
酒迎式 |
| 5月 |
17・18日 |
春季例大祭(17日 流鏑馬神事 他 / 18日 百物揃千人武者行列 他) |
| 6月 |
30日 |
大祓式 |
| 10月 |
17日 |
秋季大祭 |
| 12月 |
20日 |
御煤払 (大掃除) |
|
31日 |
除夜祭 |
|
| |
一 般
|
団体(35名以上)
|
|
大 人
|
1,300円
|
1,170円
|
|
高 校
|
|
小中校
|
450円
|
405円
|
| ●参拝時間 |
4月~10月(8:00~17:00) 11月~3月(8:00~16:00)
|
| ●参拝箇所 |
表門から奥宮までの一般公開している箇所(奥宮・眠猫・鳴龍を含む)
|
| ■ 別 納 ■ |
大 人
|
小中校
|
|
東回廊(眠猫)・奥宮
|
520円
|
370円
|
| ■特別祈祷(神職・巫女による社殿説明案内) 料金および授与品(20名以上のみ受付)
|
|
料 金
|
授 与 品
|
|
2,300円
|
神札・特製絵馬
|
|
3,000円
|
神札・特製絵馬・御神酒
|
|
所要時間
|
参拝案内40分-祈祷20分-神酒接待10分
|
| |
一 般
|
団体(20名以上)
|
|
大 人
|
500円
|
400円
|
|
高 校
|
300円
|
240円
|
|
小中校
|
200円
|
160円
|
| ●参拝時間 |
4月~10月(8:00~17:00) 11月~3月(8:00~16:00)
|
| |
一 般
|
団体(30名以上)
|
|
大 人
|
800円
|
640円
|
|
高 校
|
600円
|
480円
|
|
小中校
|
400円
|
320円
|
| ●観覧時間 |
4月~10月(9:00~17:00) 11月~3月(9:00~16:00)
但し、閉館30分前まで受付致します。
<お願い>
◇期間中祭典・行事等の都合により臨時休館或いは観覧の制限を行う場合もあります。
|
|
| 陽明門 |
 |
東照宮の代名詞とも言われる絢爛豪華な門で、あまりの装飾の素晴らしさに「時を忘れて見とれていると日が暮れてしまう『日暮し門』」などとも呼ばれている。
当時の日本の建築装飾技術の粋を集めて作られているが特に見事なのは500を越える彫刻の数々。 「竜」「息」「竜馬」「麒麟」など、伝説とされる霊獣が所狭しと並び、しかもその一体一体が今にも動き出すかのような躍動感だ。
世界遺産であると同時に、陽明門単体は、唐門・本殿などと並び国宝に指定されている。 |
| 魔除けの逆柱 |
 |
陽明門をくぐり終える左側に一本だけ紋様が逆になっている柱がある。
「魔除けの逆柱」と呼ばれている。
勿論、職人が間違えたのではなく、「完成したものは必ず崩壊する」という思想から、わざと一箇所だけ逆さにすることで「未完成」とし、建物の恒久性、ひいては徳川家、幕府の永遠の繁栄の継続を願っているものといわれている。
他にも、唐門の扉や、御仮殿・相の間天井格子の花が一箇所わざと向きを変えて配置されるなどあちこちに「魔除け」の意図がみられる。 |
| 唐 門 |
 |
間口3m、奥行き2mの小さな門だが、東照宮でもっとも重要な本社の正門。
将軍に会うことの出来る高い位の者dだけが通ることを許された。現在も、正月や大祭と国賓クラスの参拝者しか使えない。
門の上部には、中国の聖賢、下には、伝説上の皇帝:舜帝の「朝見の儀」の様子が、1本のケヤキに4列27人の彫刻で表されてる。 |
| 鳴 竜 |
 |
本地堂(薬師堂)の内天井に、34枚の天井板を使い縦6メートル、横15メートルの大きさで書かれた日光東照宮の鳴竜。
天井がその周囲から約 9 cm 凹んでいて、凹レンズのような形状の為、竜の絵の下で拍子木を鳴らすと、音が拡がらずに共鳴・反射し竜が鳴いているように聞こえる。
狩野永真安信が作製したが、堂と共に焼失。堅山南風により復元された。 |
| 眠り猫 |
 |
東照宮の数ある彫刻の中でも特に有名で、稀代の彫刻家、左甚五郎の作といわれている。
東回廊の奥社参道入り口にあるが、この眠り猫の真裏には、雀の彫刻が配置されている。
「猫が起きていれば雀は食われてしまうが、猫が寝ているので安心だ。」つまり、雀が安心して遊べる程の泰平な世の中が永遠に続くように、との意味が込められていると言われている。意外と小さいので、見落とさないように注意。 |
| 三 猿 삼 원숭이 |
 |
眠り猫と同様、左甚五郎作と言われている「三猿」。昔から「猿は病気から馬を守る」と言われていて、神馬のいる神厩舎を飾る8枚の彫刻版の1枚として飾られている。ちなみに神厩舎は東照宮では唯一、漆を塗っていない素木造りである。
8枚の彫刻はそれぞれ猿になぞらえた人間の一生を表しており、三猿は漢語の「不見、不聞、不言」を訳したもので、「(子供の頃は)この世の悪いことを見ない、聞かない、言わないように」との教えを表している。 |
| 五重塔 |
 |
石鳥居をくぐってすぐ左手に建つ朱塗りも美しい36mの塔。
1650年に建立されたが焼失し、1818年に再建された。当時の耐震耐風技術の粋を集め設計されている。
初層から4層までは垂木が建物に対し垂直に張り出る和様式、五層のみ、建物中心点より放射状に張り出す唐様式になっており、ここにも魔除けの思想が見られる。
初層の動物彫刻は十二支でそれぞれ方向を示している。 |
| 春季例大祭:百物揃千人武者行列(5月18日) |
 |
日光東照宮で一番盛大な神事で、家康の遺言により、久能山東照宮より御霊を日光東照宮に移すための行列を再現したのが百物揃千人武者行列である。正式には神輿渡御祭と言う。
1200人あまりの産子会員が、槍持ち、鉄砲持ち、武者などの装束に扮し、「3基の神輿」を守護するように、表参道を神橋近くの御旅所まで約1kmの行列を行う。渡御中はすぐ脇で行列を見物できる他、日本語・英語でのアナウンスもされ、外国からの見物客も多く訪れる。
余談ながら、大祭日は日光市内の小学校は朝礼のみで下校。児童は保護者・友人らと「社会科見学」として祭りの見学となる。 |
| 東照宮大替造にまつわる面白い話など「日光の楽しみ方」 |
|
|
|
| 日光山輪王寺 http://www.rinnoji.or.jp TEL
0288-54-0531 |

|
日光山輪王寺の起源は、766年、日光山開山の祖と呼ばれる勝道上人が現在の神橋の近くに「四本竜寺」を建立したのが始まりとされる。山岳信仰の聖地として栄えた。
「輪王寺」とは建物自体の名称ではなく、お寺やお堂、15の支院の総称。
一時衰退の危機に瀕するも、江戸時代、家康・秀忠・家光の三代に渡り将軍の相談役を務めた天海大僧正が貫主となると日光東照宮の建立もあり、目覚しい復興を遂げた。
明治の「神仏分離令」により、神仏の区別が無かった輪王寺は苦境に立たされるが、数々の困難を乗り越え、1882年に一山15院が復興し、翌83年には輪王寺、門跡呼称も復活し、ほぼ現在の形が固まった。 |
| 主な伝統行事 |
| 1月 |
1日 |
歳旦会 |
|
3日 |
外山毘沙門天縁日 |
| 2月 |
3日 |
節分会 |
| 4月 |
1日 |
開山会(勝道上人:命日) |
|
2日 |
強飯式 |
| 5月 |
17日 |
延年舞 |
| 8月 |
中旬 |
薪能 (演目・日程は年ごとに異なるので要問合せ) |
| 11月 |
25日 |
子供強飯式(於;生岡神社) |
| 12月 |
31日 |
越年護摩 |
|
| |
一 般
|
団体(35名以上)
|
|
大 人
|
900円
|
810円
|
|
小中校
|
400円
|
360円
|
| ●参拝時間 |
4月~10月(8:00~17:00) 11月~3月(8:00~16:00)
|
| ●参拝箇所 |
三仏堂内一巡・大猷院仁王門より拝殿、皇嘉門まで |
| |
一 般
|
団体(35名以上)
|
|
大 人
|
400円
|
360円
|
|
小中校
|
200円
|
180円
|
| |
一 般
|
団体(35名以上)
|
|
大 人
|
550円
|
495円
|
|
小中校
|
250円
|
225円
|
| |
一 般
|
団体(30名以上)
|
|
大 人
|
300円
|
270円
|
|
小中校
|
100円
|
90円
|
|
| 勝道上人 |
 |
「日光開山の祖」と言われる勝道上人。
735年、下野(栃木県)に生まれ少年期より山林修行を行い、766年、日光山(男体山)を開山すべく入山。四本竜寺(現在の輪王寺)を建立、現在の輪王寺や二荒山神社などの基盤を作り上げた。
また782年には念願の男体山登頂に成功、中禅寺湖を発見し、二荒山神宮寺(現:二荒山神社中宮祠)、日光山中禅寺を建立、日光山を聖地とする日光山信仰の繁栄の立役者である。 |
| 三仏堂(大本堂) |
 |
複数のお堂やお寺を集めた「輪王寺」の中心的な建物。 文字通り、三体の本尊をまつっている。
三仏堂は、東日本最大の木造の建物で、平安時代に創建された、全国でも数少ない天台密教形式のお堂である。
創建以来、たびたび移築されたが、現在の建物は、1645年、徳川三代将軍「家光」公によって建て替えられたもの。
堂前の「金剛桜」は天然記念物に指定されている。(写真はライトアップ時のもの) |
| 木彫三仏座像 |
 |
三仏堂(大本堂)にまつられた三体の本地仏。
山岳信仰に基づき、日光の三山・男体山・女峰山・太郎山を神身体とし、それぞれの本地仏である千手観音・阿弥陀如来・馬頭観音の三仏をまつった。
現存の本尊は江戸時代初期に造られた。、三体とも金色の寄木造りで、台座から光背まで約8mもある。堂入り口からは腹部付近を正面に拝するが、拝観券で参拝する際は、一旦階段を降り、台座部から見上げる形となり意外な大きさに驚かされる。 |
| 相輪橖 |
 |
三仏堂の裏手に建つ、高さ13.2mの青銅製の細長い塔。3代将軍:家光の発願により、天海大僧正が建てたもので、塔の内部には千部の経典が収蔵され、天下泰平、国土安穏を願いが込められている。塔の上部には青銅製の鈴が多数ついており、その音色を聞くと願いが叶うと言われている。
相輪塔は天台宗の象徴で比叡山延暦寺、尸羅度山曼殊院西蓮寺と並び、日本三相輪橖と言われている。 |
| 大猷院家光廟(唐門) |
 |
幼少より祖父:家康を敬愛して止まなかった家光の「死んだ後も東照大権現(家康)にお仕えする」という遺言により、1652年、息子である四代将軍:家綱により建立された。
家光が東照宮を模倣することを「畏れ多い」とはばかった為、造り・規模的にも東照宮に比べシンプルな印象だが、細部には目立たない工夫が施され独特の魅力を持っている。門をくぐるたびに石段を登っていくと、まるで水墨画の世界に迷い込んだ様な不思議な感覚に包まれる。 |
| 大猷院家光廟(皇嘉門) |
 |
大猷院において、一般参拝できるエリアと非公開とされている家光公の墓所:奥の院を隔てている門。比較的小振りな門で、様式は中国・明朝式の竜宮造りで別名「竜宮門」とも呼ばれている。黒を基調として金を散りばめた外装と真っ白な壁など、他の建物とは異なった特徴ある門である。
この門は開かずの門とされ、その奥は寺の者でも立ち入ることが厳しく規制されている。外界と声域を隔てる門でもある。 |
| 勝道上人の日光山開山にまつわる面白い伝説など「日光の楽しみ方」 |
|
|
|
|
|
| 日光二荒山神社 http://www.futarasan.j TEL
0288-54-0535 |

|
二荒山とは現在の男体山を指し、勝道上人が二荒山を中心とする霊地を山岳信仰の聖地とすべく入山し、大谷川(だいやがわ)北岸に四本竜寺(輪王寺の起源)、本宮神社を建てた。これが二荒山神社の始まりである。こののち、数度の失敗の後、大願の二荒山登頂を果たし、山頂に奥宮をまつり、中禅寺湖湖畔には二荒山中宮祠を建立、ほぼ現在の形となる。
二荒山神社は古くから関東の守り神として信仰を集めてきた。東照宮建立の際は、幕府より神領を寄進され、社殿を造営するなどして、更なる信仰を集めた。
現在でもその社地は、男体山・女峰山・太郎山の日光三山を含む日光連山8峰(奥白根山・前白根山・大真名子山・小真名子山・赤薙山)の他、華厳の滝、いろは坂などをも含み、総面積3400ヘクタールという壮大な境内を誇る。これは、伊勢神宮の次ぐ広大さである。
|
| 主な伝統業行事 |
| 1月 |
1日 |
歳旦祭 |
| 2月 |
1~3日 |
節分祭 (3日 ガラ蒔き) |
| 4月 |
13~17日 |
弥生祭 |
|
|
|
| 毎月 |
第2土曜 |
だいこくまつり(12月を除く) |
|
|
| ●参拝時間 |
4月~10月(8:00~17:00) 11月~3月(9:00~16:00)
|
| |
大 人
|
小中校
|
|
本社神苑入園料
(化灯籠含む)
|
200円
|
100円
|
|
日光神楽
|
500円(10名以上) |
|
特別参拝神楽
|
1,000円(10名以上)
|
|
| 神 橋 |
 |
日本三大奇橋(山口県錦帯橋、山梨県猿橋)の1つ。 「日光開山の祖」と言われる勝道上人が日光山入山を試みた際、大谷川の絶壁に行く手を阻まれたため護摩を焚いて祈祷したところ、深沙王が現われ、二匹の蛇を投げた。二匹の蛇は川に架かり見る間に背中から山菅が生えて橋となったーという伝説が残っている事から、別名「山菅の蛇橋」とも呼ばれている。
家光の「東照宮大替造」にあわせ朱塗りの橋となり「平成の大改装」などを経て現在の美しい姿となった。 |
| 二荒霊泉 |
 |
神苑の朋友神社先の鳥居奥に位置し、本殿後ろの恒例山から湧き出ている、眼病に霊験ありと言われる「薬師霊泉」と滝尾神社境内の天狗沢より湧き出る「酒の泉」を集め引かれたもの。
「酒の泉」で酒を造ると銘酒ができると言われ地元の酒蔵元に信仰されている。
また、パワースポットとしても知られ、「お水とり」などの参拝者も後を絶たない。 |
| 胴灯篭(化け灯篭) |
 |
本社本殿透塀に沿って立つ多数の石灯籠とともに並ぶ唐銅製春日造りの灯篭。
その昔、夜になり火を灯すと、ゆらゆらと妖しげな姿に変化し物の怪と間違えられ警護の侍によって切りつけられたといい、今も当時の刀創がいくつも残る。別名「化け灯篭」。
陽が沈むと漆黒の闇に包まれる山内で、ゆらゆらと揺れる灯篭の不気味な明かり、実は燃料となるナタネ油を舐めに来たモモンガが妖しく見間違われたものとの説もある。 |
| 弥生祭(4月17日 本夜祭) |
 |
「日光に春の訪れを告げる祭り」として古くから市民を上げての盛り上がりを見せる祭り。神事は13日の八乙女舞などで始まるが、見どころは「花家体」が市内に繰り出す16日の宵祭り(観光協会主催)と17日の本祭り。子供達のやよいばやしを乗せた各町内の花家体が市内を周り境内に集結。二荒山神社内の神事が終了した後、拝殿前を回り各町内に戻っていく。
(旧)日光市内では、夕方になると、各町内の会所に子供達が集合し、弥生祭に向け子供囃子の練習に励み、その音が薄暮れの町内に響く情景がそこここにみられる。 |
| 神橋にまつわる面白い伝説など「日光の楽しみ方」 |
|
|
|
|
|